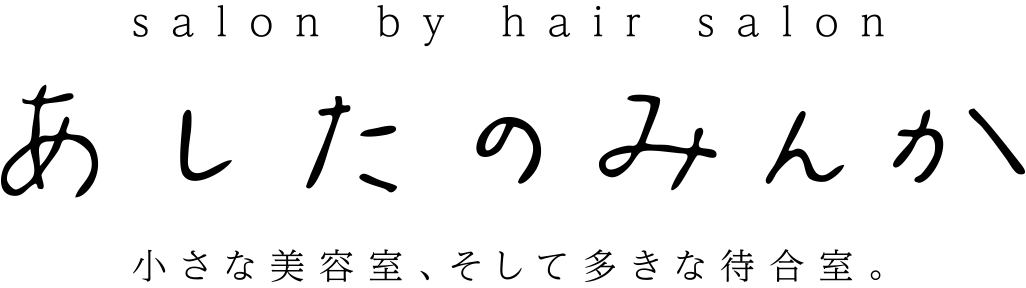その手に宿るもの

「わたしの手、おばあちゃんみたいですね。」
撮影を終えた写真を見て、直子さんは少し恥ずかしそうにそう言いました。
「いえいえ見てください。わたしもです。」
そう言ってわたしは節くれ立ったカッサカサの自分の手を広げてみせました。
同い歳のわたしたち。
同じだけの時間を、ひたすら動かし続けてきた互いの手を見て笑い合ったのでした。
平成最後の日と話題になっていた昨年の4月30日。
その日は雨曇りでいつもより少し肌寒さを感じるお天気模様でした。
明日から元号が変わる、その節目の日に、わたしは撮影のため笠間へ行っていました。
作り手である直子さんと初めて知り合ったのは、遡ることもう少し前の平成29年の夏でした。
きっとお互いに良い出会いとなるはず、と、ある方がわたしたちを引き合わせてくださったのです。
いつかその手仕事を間近に拝見してみたいと密かに夢を膨らませていたところ、ご本人から制作工程の撮影の依頼をいただき、アトリエへとお邪魔させていただく機会となったのでした。
アトリエは工芸の丘の近くの小さな一軒家でした。
直子さんはそこで織り機と一緒に暮らしていました。
仕事と暮らしが溶け合い、寄り添い合っているかのようでした。
慎ましく静かなその暮らしの風景は直子さんの印象そのままだったのでした。

直子さんは手漉きの和紙から糸を紡ぎ一枚の布を織りあげます。
仕立てまでには数多くの工程があり、その一つ一つには私たちが想像に及ばないほど手間がかけられています。
その全てを一人、手作業で行うのです。
そうして出来上がる布は「紙布(しふ)」と呼ばれています。
直子さんは紙布を織る作り手なのです。
紙漉き、染め、織り。
これまで学び歩んできた道は、まるでいつか「紙布」と出会うことが運命付けられていたのではないかと思えてなりません。
わたしはあえて「作家」でもなく「職人」でもなく、「作り手」と呼びたい。
そしてきっと本人も「作り手」という表現を受け入れてくれると、わたしにはなんとなく分かるのです。



ファインダーを覗きながら、わたしは感動で胸がいっぱいでした。
居るけど居ない。
そこには人の主張がなく、ものが生まれてゆく、ただ美しいものが生み出されてゆく、その一部として人間の手が控えめに存在していたことに、わたしは深い感動を覚えたのでした。
そして紙に触れるその手には、直子さんの素材に対する愛と敬意がありました。
一枚の紙は徐々にその姿を変えながらうつくしさを増していきます。
紙と人の手が共鳴しあい、光を放っているかのようでした。



楮(こうぞ)という1本の木を、人々は暮らしの「用のもの」として紙へと生まれ変わらせてきました。
やがて貴重な資源である紙を無駄にしまいと、細く裂いて糸状にして織って身に纏ったのがはじまりと言われています。
紙布は繊維が細かいため丈夫でその上風通しがよく、洗うたびに柔らかい風合いと素朴で温かな表情があります。
悠久の歴史の中で、人は地道に手を動かし、必要なものを生んできました。
人から人へと伝えられ、より美しい形となって現代に残ってきたこと、そして、人の手から生まれたこのうつくしいものを、これからも残していかなければと切に感じたのでした。




今回の表紙の写真は、まさに紙が糸へと生まれ変わる瞬間を写したものです。
糸と糸とを繋ぐ、この作業で生まれる「節(ふし)」は、手仕事でしか生まれない表情として布の上に現れます。
このぽつ、ぽつとした可愛らしい節に、わたしは決して見ることができないはずの作り手と糸との間に流れる静かで満ち足りた時間を見ているような気がしてくるのです。
撮影からの帰り道、興奮が覚めやらないわたしの紅潮した頬に、雨上がりの夜風が心地よく、わたしは再び胸がいっぱいになったのでした。
あれから1年。
時代は風のようにあっという間に違う世界を連れてきました。
たくさんの人が立ち止まり、どう生きていくべきかを自問しながら今を生きているのではないかと思います。
わたしは1年前に胸を熱くしたあの時の光景を、ここ最近何度も思い出しては写真を見返していました。
今、あらためて思うのです。
手に宿る何かが、誰かの心に明かりを灯している。
どうかたくさんの作り手と言われる人たちが、その手を止めてしまわないように、手を止めざるを得ないことになってしまわないように。
手から手へ、うつくしいものが未来へと繋がってゆきますように。
ps.
いつの日か直子さんの紙布をみなさんにご覧いただきたいと思っています。
20年という歳月を手仕事にかけてきたわたしたちですが、それでもまだ各々が長い長い旅の途中にいます。
紆余曲折あるけれど、旅する友の存在がいつもわたしに力をくれています。